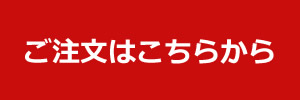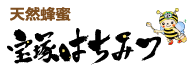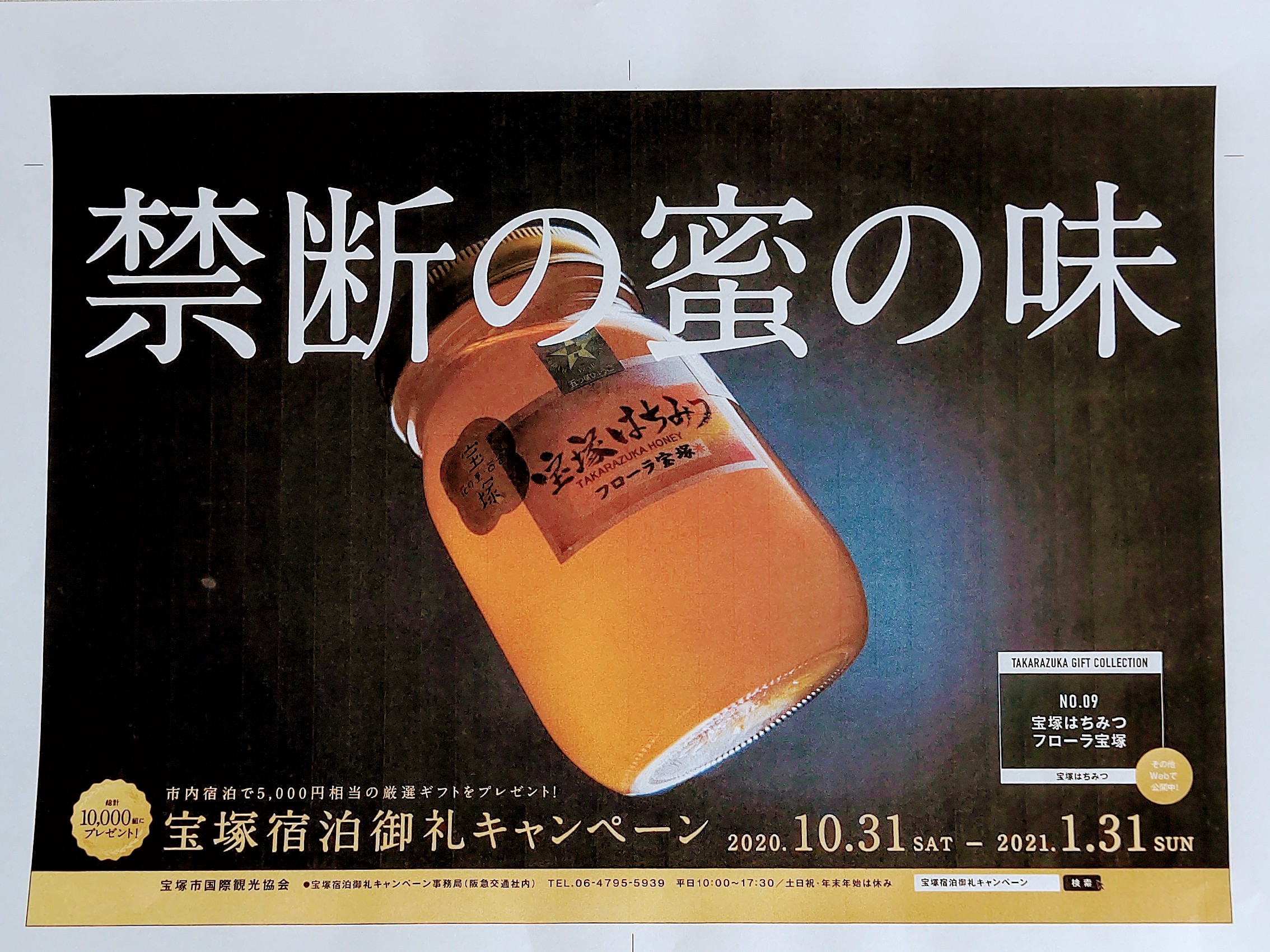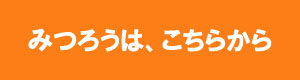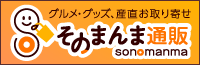養蜂場日記
怪獣イノゴン!
2008年11月19日 / 養蜂場日記
 夜の田んぼに現れる「怪獣イノゴン」の足跡・・・正体はイノシシです。
夜の田んぼに現れる「怪獣イノゴン」の足跡・・・正体はイノシシです。
稲刈りの終った田んぼは、電気柵が撤去されます。早速、イノシシ君たちが侵入し、好物のミミズを探したり、転げまわって“泥入浴”を楽しんだり・・・夜間は彼等のパラダイスになるのです。
中にはもっと不埒者もいて、稲刈り前の田んぼに侵入して、収穫を台無しにしてしまう時もあり、里山では「はなつまみ者」「厄介者」の烙印を押されています。
夜間に行動するため、私は目撃したことはありませんが、養蜂場の周辺にも夜間行動の痕跡を見かけます。
厳しい自然の中で生きていくのは大変だろうけど、あんまりやり過ぎないようにね!
居残り?
2008年11月18日 / 養蜂場日記
 夏の強い直射日光から巣箱を護るために、木々を植えています。若木の生長のために雨水を利用。
夏の強い直射日光から巣箱を護るために、木々を植えています。若木の生長のために雨水を利用。
タンクに雨水を貯め、汲みだし用には、使わなくなったバスタブを利用しています。
どうもこのカエル君は、満水になっていたバスタブで水遊びを楽しんでいたところ、水が汲みだされ、水位が下がって外に出られなくなったようです。
仲間が冬眠に入った後も、ここに閉じ込められていたのです。
まさしく“井の中の蛙”状態で、幾日かを過ごしていたのでしょう。
小さな体をそっとつまんで、柔らかい土の上に戻してやりました。遅ればせながら、冬眠に間に合ったようです。
ラスカルの好物
2008年11月11日 / 養蜂場日記
 この時期になると、養蜂場に行く道すがら、よく見かける光景です。特に今年は柿のできが良く、文字どうり「鈴なり」です。あまりの重さに折れている枝もあります。すっかり葉が落ちて実だけが残った柿の木が、夕陽に映えてオレンジ色に耀いています。
この時期になると、養蜂場に行く道すがら、よく見かける光景です。特に今年は柿のできが良く、文字どうり「鈴なり」です。あまりの重さに折れている枝もあります。すっかり葉が落ちて実だけが残った柿の木が、夕陽に映えてオレンジ色に耀いています。
この柿の実は、最近急激に増えているアライグマの、格好のターゲットになっています。種だけ残して綺麗にかじられた柿の実をよく見かけます。
先日も、近くの菜園から出てきた生き物とバッタリ出会い、目が合いました。最初、タヌキ!と思いましたが、あれはどう見てもアライグマでした。
以前、アライグマ「ラスカル」と言うアニメがはやり、その可愛らしさに、沢山の人がペットとして飼いました。(家にもラスカルの小型扇風機があります。スイッチがラスカルの形になっていて、それを回すと風が出ます^^;)
でもその可愛い外見とは違って、かなりの暴れん坊だそうです。
みつばち物語
2008年10月30日 / 養蜂場日記
 「最新のお知らせ」欄にも出ていますが、この度「コスモ アースジン」という雑誌が刊行されました。
「最新のお知らせ」欄にも出ていますが、この度「コスモ アースジン」という雑誌が刊行されました。
これに、うちが手掛ける「みつばち物語」が連載されています。
”ピース”という名の働きバチが、ミツバチの生態や暮らしぶりをご案内していくものです。
楽しみながらミツバチの事がよく分かる記事です。ぜひお読みください。
これは、そのページです、イラストが可愛いでしょう?
ぜひ手に取って御覧頂きたいです。
そして、今後のピースの活躍をお楽しみに (^^)/
詳しくは「最新のお知らせ」を御覧下さい・・・
稲干し
2008年10月30日 / 養蜂場日記
 養蜂場に行く途中、刈入れの終った田んぼで稲干しを見かけました。
養蜂場に行く途中、刈入れの終った田んぼで稲干しを見かけました。
刈り取った稲を稲架に掛けて、天日干ししています。
今は刈り取ると同時に、脱穀・袋詰めまで機械で自動的にやってしまう所もあります。
コンバインで稲刈りをしながら進み、後ろには脱穀されたお米の袋が降ろされていくという、昔では考えられないスピードでお米が出来上がっていきます。
ですから、このように稲を干す、昔ながらのやり方をあまり見掛けなくなりました。
懐かしくなって写真に収めたところです。
空一面の・・・
2008年10月26日 / 養蜂場日記

自宅の窓から見た夕焼けです。
空一面が赤く染まって、見とれてしまいました。
養蜂場とは関係ありませんが、こんな見事な風景は載せたくなるものです。
秋祭り
2008年10月26日 / 養蜂場日記
 養蜂場から帰る道すがら、秋祭りの檀尻(だんじり)に出会いました。
養蜂場から帰る道すがら、秋祭りの檀尻(だんじり)に出会いました。
秋の収穫を、神に供えて感謝する祭りです。
この時期は、あちこちで檀尻やお神輿(みこし)が繰り出します。
ちなみに檀尻とは、車の付いた屋台のことで、関西以西の呼び名、関東では山車(だし)と言います。
威勢の良い笛や太鼓の音が、何かしら郷愁をかき立てます~~故郷の友達はみんな、元気かな・・・
赤とんぼ
2008年10月26日 / 養蜂場日記
 夕焼け小焼けの赤とんぼ~とまっているよ~竿の先~♪
夕焼け小焼けの赤とんぼ~とまっているよ~竿の先~♪
作業の手を休めてふと見ると、目印のために立てた杭のテッペンに赤とんぼが羽を休めていました。
見上げると、沢山の赤とんぼが養蜂場の上空をスイスイ飛び回っています。赤とんぼの代表は「秋茜(あきあかね)」と言います。普段の体は黄褐色ですが、成熟した雄が赤くなり、秋に群れて飛びます。
蜂にとっては害敵ですが、秋の空に赤とんぼはやはりぴったりですね・・・
秋の空
2008年10月18日 / 養蜂場日記
 一日の仕事が終わり、汗ばんだ体に夕風が涼しく感じられます。
一日の仕事が終わり、汗ばんだ体に夕風が涼しく感じられます。
ふと見上げた養蜂場の上空一面にうろこ雲、秋ですネ・・・
秋の空が高く感じるのは、雲が高い所にできるからだと聞いたことがあります。
そろそろ蜂達も冬の準備に入ります。この秋に生まれる蜂達が越冬し、春の子育てをすることになります。
今年の夏の暑さは異常でした、蜂達も涼しくなってホッとしていることでしょう。
 10月4日に登場したカマキリ君が、ころもがえして参上。
10月4日に登場したカマキリ君が、ころもがえして参上。