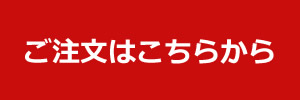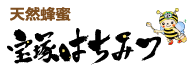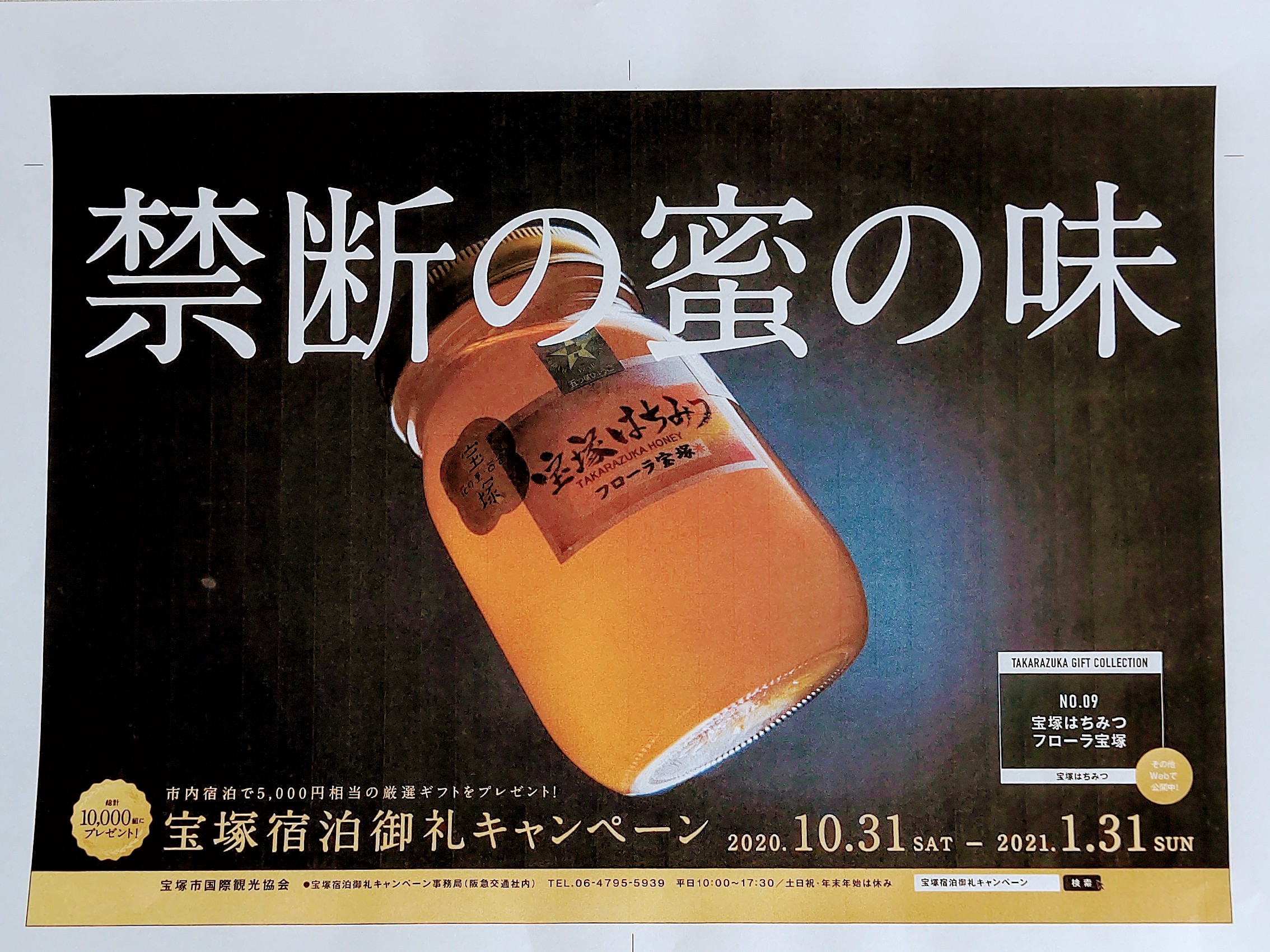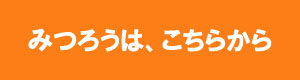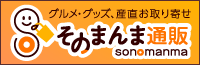養蜂場日記
「福」
2009年11月6日 / 養蜂場日記
 我が家のリビングに飾ってある額です。実に力がこもった字です。
我が家のリビングに飾ってある額です。実に力がこもった字です。
これを書いてくださった方は、ある気功の先生で、宝塚はちみつのラベル、及び、このホームページの題字を書いてくださいました。
うちの蜂蜜のラベルの真ん中に描かれた金色の円、あれは登る朝日をイメージしたものですが、そこに大きなパワーがこめられています。
それを感じて、中味がなくなっても、ラベルの貼られたビンだけを飾っていらっしゃる方もおられます。
毎年1月10日、西宮神社に於いて、福男日本一を選ぶご神事があります。
今年の全国のニュースで、福男に選ばれた男性が「福」の額を高々と掲げていましたが、それと同じ時に書かれた三つの内の一つが、うちにあるこの額です。
蜂蜜活用法 7 レモンジンジャーシロップ
2009年11月3日 / 養蜂場日記
 随分久し振りの更新になってしまいました。
随分久し振りの更新になってしまいました。
きょうはお客様から教えて頂いたレシピをご紹介します。
材料:しょうが 150gくらい
はちみつ 80gくらい
レモン 2個
水 300ccくらい
☆しょうがと蜂蜜はお好みで加減してください。
1.しょうがは洗って汚れを落とし、薄切りにしてミキサーにかける
2.鍋に、水、しょうが、蜂蜜を入れて、沸騰したら8分くらい煮る。
3.仕上げにレモンの絞り汁を入れて1分くらい煮たら出来上がり。
ザルでこして冷蔵庫で保存します。
お湯で4~5倍に薄めて飲むと、とても暖まります。お好みで、炭酸水で割ってジンジャエール風にしたり、サワーで割ったりと、用途はいろいろ。市販のジンジャエールシロップは砂糖が多いので、蜂蜜で作るほうがヘルシーですね ♪
おまけ:残ったしょうがのカスは、少し蜂蜜を足して、一煮立ちさせてジャムにしたり、そのまま紅茶に入れると美味しいジンジャーティーになります。
以上、横浜のMさんから頂いた文をそのまま引用させて頂きました。
と~っても美味しそうです!!皆様もぜひ作ってみてください。
Mさん、ありがとうございました!
柿ボール?
2009年10月19日 / 養蜂場日記
 ワンワン!ワンッ! 哲平がテーブルを見上げてさかんに吠えています。
ワンワン!ワンッ! 哲平がテーブルを見上げてさかんに吠えています。
テーブルの端に置いてあった、ちび柿を見つけたようです。前回の日記に出した小さい柿です。
哲平にとって、小さくて丸い物は全部「ボール」なのです。「新しいボールだ!ちょうだい、ちょうだい!」と言っているのでしょう。
床に転がしてやると、凄い勢いで飛びかかってくわえ、意気揚々とハウスに持って入りました。ハウスの中で、私が柿を取りあげて投げるのを、今か今かと待ち構えています。
こうして朝からボール投げの相手をさせられることになりました。
・・・以前夕暮れ時、もう薄暗くなって散歩していた時のことです。畑の横を通りかかると、いきなり哲平が興奮しだしました。
畑の中に入ろうと私をグイグイひっぱります。その畑は収穫が終わり、作物は何も無くなっています。
何かあるのか?と目をこらしてみると、薄暗い中に、何か白っぽく丸い物が・・・
近くに行ってみると、それは1個だけポツンと取り残されたキャベツでした。
離れた所から見ると、丁度いい大きさのボールに見えたんですネ。
「大きいね、それにボールじゃなかったね・・・」と、がっかりしている哲平を慰めつつ家路につきました。
”小さいカキ”見ぃつけた!
2009年10月16日 / 養蜂場日記
 田んぼの用水路脇のこじんまりした藪の中に、小さな秋の実りを見つけました。
田んぼの用水路脇のこじんまりした藪の中に、小さな秋の実りを見つけました。
自然に生えた2メートル程の柿の木に、可愛らしい実がなっています。
小さいながらも、ちゃんとした柿の実の形をしています。
直径約3センチ。成長段階ではなくて、ちゃんと成熟した実です。
秋の光の中で、「俺は柿だぞ~、私も柿よ~」と、その存在を主張するかの如く、まさしく“柿色”に輝いていました。
優良物件に居候・・・カマキリ
2009年10月14日 / 養蜂場日記
 養蜂場の巣枠の上に陣取ってミツバチを狙っています。時には巣門まで降りていってミツバチを食べてしまいます。
養蜂場の巣枠の上に陣取ってミツバチを狙っています。時には巣門まで降りていってミツバチを食べてしまいます。
しかし、オオスズメバチに比べれば被害は微々たるもので、群れの存続には全く影響がないので、こちらも寛大な心で見守っているところです。
奴等はそれを良いことに我が物顔で闊歩し、巣箱に卵を産みつける者まで出る始末!・・・それを許しているこちらも度量が大きい!?
彼らにとって、ここはとても住み心地の良い「優良物件」であることは間違いありません。カマキリは他の害虫も取ってくれるので、共存共栄の平和を維持しているところです。
雌は体が大きくて動きが鈍く、雄は小さくてすばしっこいのだそうです。
カマキリの雌は交尾の後、雄を食べてしまうというのはよく知られていますが、中にはさっさと逃げおおせて、また別の雌と交尾する要領の良い雄もいるようです。(これを知ってなんだかホッとしたのは、私だけでしょうか~~)
もっともカマキリは肉食で、目の前で動くものは皆、餌と認識して飛びかかってしまうらしいのですが。
北陸ではカマキリが高いところに産卵すると大雪になるという言い伝えがあります。雪に埋もれてしまわないように、高い所に産み付けるのだそうです。
これは単なる伝説ではなく、科学的なデータがあるという事です。
秋晴れの下の獅子舞
2009年10月13日 / 養蜂場日記
 我が家から養蜂場まで30分の道のりの途中、五つの集落を通り過ぎます。
我が家から養蜂場まで30分の道のりの途中、五つの集落を通り過ぎます。
今日(10月12日)、その中の一つに差し掛かったとき、法被を着た10人ぐらいの集団が目に入ってきました。
ピーヒャラ,ピーヒャラと笛の音も賑やかに聞こえてきます。
秋祭りです。しかし、神輿も山車も見当たりません。その代わり、なんと、行列の先頭を歩いているのは“獅子頭”です。
獅子頭は一軒の民家に入って行きました。
車を停めて、助手席に置いてあるカメラを掴み、現場に直行。 すでに、玄関前で獅子舞?お神楽?が始まっていました。
最初は剣を手に、その後は御幣(ごへい)を振っての舞です。
後ろには10人ほどの賑やかなお囃子(はやし)がついています。
秋晴れの下の獅子舞。おそらく五穀豊穣に感謝する風習として、昔から受け継がれてきたものなのでしょう。
なんだか心豊かな気持になり、養蜂場まで口笛交じりで運転しました。
今日は楽しいお祭り日!
2009年10月12日 / 養蜂場日記
 養蜂場からの帰り道、秋祭りの山車に出会いました。
養蜂場からの帰り道、秋祭りの山車に出会いました。
子供用も含めて3台あります。
揃いの法被を着た子どもたちの顔が楽しそうに上気していました。きっと、昔の“村”の時代から連綿と受け継がれてきたお祭りなのでしょう。
「村の鎮守の神様の、今日は楽しいお祭り日、ドンドンヒャララ~ドンヒャララ~ドンドンヒャララ~ドンヒャララ~朝から聞こえる笛、太鼓~♪」
運転しながら思わず口ずさんでいました。
子供時代に憶えた歌は、すんなりと出てくるものですね。
ハチミツ活用法 7 ふくれ菓子
2009年10月10日 / 養蜂場日記
 子供時代は田舎に住んでいたこともあり、美味しいお菓子など店に売っていませんでした。
子供時代は田舎に住んでいたこともあり、美味しいお菓子など店に売っていませんでした。
学校から帰ると、いつも母が作ってくれていたオヤツ。小麦粉と黒砂糖をセイロで蒸して作る「ふくれ菓子」です。
手で掴むと皮が指にまとわり付き、その皮の付いた指を舐めながら遊びに飛び出して行ったものです。
しばらく遊ぶととまた家に帰り、残りのふくれ菓子を持って出ます。
片手にふくれ菓子を持ったまま走り回って遊んでいたのを覚えています。時々ちぎって友達に上げたりしていました。
そのふくれ菓子、今は家内が作ってくれます。
セイロの代わりに大きい鍋にお湯を沸し、ステンレスのボールに小麦粉とハチミツ、ふくらし粉をまぜてトロトロにした種を入れて蒸します。
ハチミツと黒砂糖の違いはありますが、私にとってはとても懐かしい素朴な味です。
ロボット君とレンゲの花
2009年10月7日 / 養蜂場日記
 このロボット君?実はレンゲの種まきには欠かせないものです。
このロボット君?実はレンゲの種まきには欠かせないものです。
その名は“動噴(どうふん)”―――動力噴霧機のことです。
本来は粒状の肥料や薬剤を散布するためのものですが、広範囲に種を播くときにも使われます。
何千坪何万坪の田んぼに、レンゲの種を播く時の必需品です。
種を満タンに入れると、重さは20キロにもなります。
これを背中に担いで、田んぼの畦を歩きながら種を播いていきます。
背中の“動噴”のエンジン音はすさまじいものです。
このエンジン回転を利用して、強力な送風を起こし、手で持った長さ2メールほどの筒からレンゲの種を噴出します。
重くて大変な作業ですが、美味しいレンゲ蜜の収穫のためには、どうしても欠かせないものなのです。
これは9月から10月初旬にかけて行ないます。
翌春、4月10日頃から花が咲き出し、まるでピンクの絨毯を敷き詰めたような見事な風景が現われます。
ガマズミ
2009年10月6日 / 養蜂場日記
 昨年も登場しました、艶やかなまん丸い実が可愛いガマズミです。
昨年も登場しました、艶やかなまん丸い実が可愛いガマズミです。
秋になると、養蜂場の周辺は真っ赤な実でにぎやかになります。
今年は、この実でガマズミ酒を作ってみました。
ガマズミの実は房ごと枝から取って丁寧に洗い、一粒ずつ実を取ります。
ザルなどにあけて、布巾やキッチンペーパーなどで水気をしっかり切ります。
熱湯消毒したビンに実を入れ、35度のホワイトリカーを注ぎます。ここで、一般的には氷砂糖を入れます。(ガマズミの実の半分から4分の1位)
うちで作るものは、氷砂糖ではなくもちろんハチミツを使います。柔らかい甘味で風味豊かに仕上がります。
3ヶ月位で実を取り出して、冷暗所に保存します。
綺麗な赤い色は段々と薄くなるので、1年位で飲みきってください。
クリスマスの雰囲気にピッタリのお酒です。