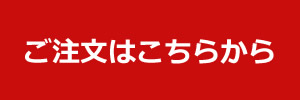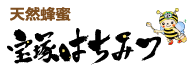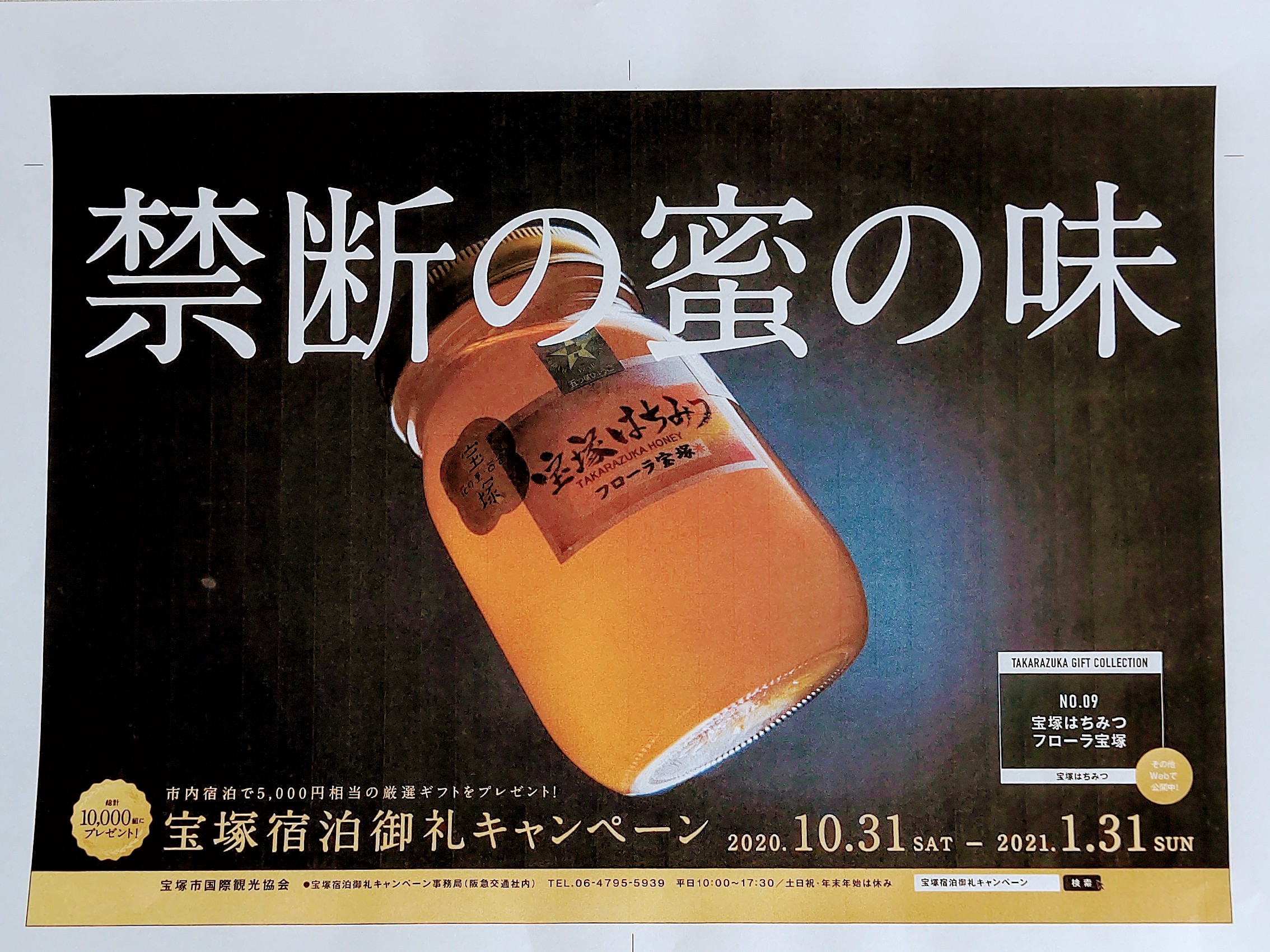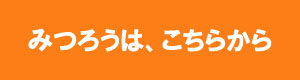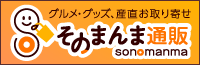養蜂場日記
冬の訪問者
2009年11月29日 / 養蜂場日記
 カンカンカン カンカンカン という音が、小刻みにリズミカルに聞こえてきます。
カンカンカン カンカンカン という音が、小刻みにリズミカルに聞こえてきます。
今年も来たな!と、にんまりする瞬間です。
冬になると里山に下りてくる、アカゲラというキツツキ。
夏の間は、深山や比較的高地の山林で過ごし、冬季に低地の山里で生活する留鳥です。
下腹部は赤、全体は黒白のまだら模様、雄だけ後頭部が赤といういでたちです。
リズミカルな音は、枯れ木を力いっぱい突いて出すもので、縄張りを宣言するドラミングという行動です。
養蜂場を開設したその年の冬に、生まれて初めてドラミングの光景を目にしました。
テレビでしか見たことのない姿にいささか興奮したものです。
冬枯れの林の中を動き回る、赤、白、黒の羽毛がとても鮮やかに目に写ります。
来春までの短い付き合いですが、耳と目で楽しませてもらいます。
”ザ・ラスカル”?
2009年11月26日 / 養蜂場日記
 実をいっぱい付けた柿の木の下に、きれいにかじった歯跡のある柿の実の残骸がたくさん散らばっています。
実をいっぱい付けた柿の木の下に、きれいにかじった歯跡のある柿の実の残骸がたくさん散らばっています。
見事な食べっぷりです。どこかの悪がき連中の仕業でしょうか?いいえ、今、各地でその悪名が知られつつある、ギャング。
その名は“ザ・ラスカル”という新興勢力の仕業です。
各地でアライグマの被害が報告されています。農作物の被害だけでなく、京都や奈良では神社やお寺に住み着いて文化財を傷つけたりと、その悪名を日々新たにしています。
養蜂場の周辺地域でも、アライグマによると思われる被害が増えています。近くの菜園から出てくる“ラスカル君”を見かけたことがあります。
最初は猫でもない、犬でもない、何だろうと思ったのですが、尻尾の縞模様でアライグマと確認できました。
近くの農家の主婦は外出から帰ってきて、屋根の上に座っているアライグマと目が合い、しばらく睨み合いを続けたとのこと。
可愛らしい見かけによらず、結構凶暴なところがあるので注意したほうがよいと言われています。
手先の器用なアライグマの食べ跡は、まるで人間が食べたように見えます。柿の実も、ヘタとその周囲の部分だけ綺麗に残して食べています。
「アライグマ ラスカル」というアニメで人気が出て一挙に飼う人が増え、日本中に広まりました。
「誰も好き好んで日本に来たんじゃないよ」と言っているのではないでしょうか?
北米の大自然の中で自由に駆け回っていた時代、デービークロケットが活躍した頃の先輩達を羨ましく思っていることでしょう。
可愛いお客さん
2009年11月24日 / 養蜂場日記
 晩秋から早春までのシーズンオフの時期は、養蜂場の整備や補修等に時間をかけます。
晩秋から早春までのシーズンオフの時期は、養蜂場の整備や補修等に時間をかけます。
土を掘り返す作業の時に必ず現われるのが“ジョービタキ”という可愛い小鳥です。
秋になると日本各地に姿を現す渡り鳥。掘り返した土に潜む虫が目的です。
2~3メートルの距離を保ちながら、新しい土の上をちょこまかと歩き回り、せわしなく餌をあさります。
遠いシベリヤから、はるばる日本海を越えて飛来した小さな体。地球上で同じ時間を分かち合う仲間として、いとおしさを感じます。
黒、白、橙色の目立つ配色のオスと、薄茶色の地味な羽色のメス。仲良く夫婦で訪問してくれる時もあります。
子供時代、故郷の田舎ではこの鳥はとても大事に扱われていました。捕まえたり、傷つけたりしてはならないと教えられていました。
特に、農耕馬のいる家庭の子供たちほど、この教えに忠実だったようです。教えを破れば、その家の馬に良くないことが起こると言われていたからです。
田畑を耕したり、すき返したりする時に飛んできて、地中の害虫を食べてくれるジョウビタキは、遠い昔から大事な益鳥として保護されていたようです。
いつも陽気なコジュケイ君
2009年11月23日 / 養蜂場日記
 チョッ~トコイ、チョッ~トコイ と大きく陽気な鳴き声が聞こえてきました。
チョッ~トコイ、チョッ~トコイ と大きく陽気な鳴き声が聞こえてきました。
キジの仲間のコジュケイです。鶉(ウズラ)よりひと回り大きく、全体が枯葉色の羽毛。
いきなり、足もとから飛び立って、心臓も止まりそうな思いをさせてくれる奴です。
中国南部や台湾がもともとの生息地。
日本には明治時代に狩猟鳥として輸入され、本州太平洋岸、四国、九州に広がったのだそうです。
5月頃になると養蜂場の周辺でも、6-7羽のヒナ鳥を連れた夫婦を見かけるようになります。
前後を親鳥に護られて、一列で進む集団に、思わず笑みがこぼれます。黄色の体に茶色の筋が入った“ウリ坊”たちが、必死に親鳥について行く様は実に愛らしいものです。
一時、爆発的に増えたコジュケイでしたが、現在は数が減ってきているとのこと、自然環境の変化が原因なのでしょうか?
傘?
2009年11月19日 / 養蜂場日記
 久々の「これはなんでしょう?」シリーズ。
久々の「これはなんでしょう?」シリーズ。
養蜂場の近くで菜園をしているSさんから頂いた、巨大な椎茸です。
哲平の頭も隠れるほど大きい物ばかり。こんな立派な椎茸を沢山頂きました。
巨大というと、子供のころ傘の代わりにした、里芋の大きな葉っぱを思い出します。
外で遊んでいて急な雨に降られると、畑の里芋の葉をもぎ取って、傘のように頭にかざして走って帰ったものです。
あたかも防水加工をしてあるかのように、雨のしずくが葉っぱの上で大きな玉になって転がり落ちていきました。
さて、しばらくは椎茸づくしのぜいたくな健康食が続きます。
俺は”国鳥”
2009年11月17日 / 養蜂場日記
 養蜂場の周辺一帯は禁猟区です。沢山の生き物が伸び伸びと生活しています。
養蜂場の周辺一帯は禁猟区です。沢山の生き物が伸び伸びと生活しています。
特に目にすることが多いのが“雉(キジ)”です。
毎年秋になると、雄同士の闘いが始まります。甲高い鳴き声とともに、風を切る羽音がして、地上5~6メートルの高さで追いかけあっている姿を見ることもしばしばです。
おそらく、来るべき繁殖の季節のための雌をめぐる争いなのでしょう。
仕事をしている私の頭上2メートルほどの高さを飛んでいった時には、びっくりすると同時に、豊かな自然の中で仕事ができる幸せを感じたものです。
地味な羽色の雌に比べ、明るい緑、濃い緑、輝く紫の羽色と、真っ赤な頬が特徴の雄の美しさは格別です。
野生のキジの鮮やかな羽毛は、動物園などで飼育されているものにはない、生き生きとした美しさがあります。
人間の姿を見ると、そそくさと藪に逃げ込む雌に比べて、雄は堂々としています。
その歩みもゆったりとして、時々立ち止まり、じっとこちらを観察したりする余裕を見せます。「俺は国鳥だぞ。無礼は許さないぞ」とでも言っているかのようです。気品すら感じるその姿に、感動を覚えます。
オケラちゃん
2009年11月14日 / 養蜂場日記
 養蜂場で穴掘りをしていると、ミミズや昆虫の幼虫など出てきます。
養蜂場で穴掘りをしていると、ミミズや昆虫の幼虫など出てきます。
今日は“オケラ”が2匹出てきました。おそらく番(つがい)ではないかと思われます。
正式には“ケラ”。
調べてみると、いろいろなことが分かりました。
彼らはコオロギの仲間だそうです。そういえば、モグラみたいな頭部は別として、その他はコオロギそっくりです。
主に田んぼなどの湿地に生息するそうですが、近年はその数が減ってきているとのこと。
徳川時代、江戸周辺の農家には“オケラ”を採集して幕府に納めるという義務が課されていたそうです。
理由は、大奥で飼われていたたくさんの鳥達の餌にするため。
不思議と野生の鳥もこの虫を好んで捕食している様子、鳥類にとっては“大トロ”の味なのでしょうか?
来年の夏に向けて
2009年11月13日 / 養蜂場日記
 夏の直射日光から巣箱を護るため、今年は鉄パイプを組み、葦(よしず)を掛けるようにしていましたが、台風の時に一部が倒れてしまいました。
夏の直射日光から巣箱を護るため、今年は鉄パイプを組み、葦(よしず)を掛けるようにしていましたが、台風の時に一部が倒れてしまいました。
現在、支柱の補強工事をしています。どんな強風にも耐えるような頑丈なものです。
深さ50センチの穴に埋め込んだ鉄パイプの基礎を、厚さ15センチのブロックで挟み、それをコンクリートで固定して土をかぶせるというものです。
支柱だけでも約50本、さらに、その支柱に横に鉄パイプを差し渡す作業があります。
養蜂というより、土木工事の毎日です。
作業の手を休めて見上げる空にはうろこ雲が広がっています。汗をかいた体をひんやりとした秋風が撫でてくれます。
思いは、すでに来年の花の季節にとんでいます。
健康で強大なミツバチの群を育成するためには、どんな苦労も惜しまないのが養蜂家なのです。
空中戦
2009年11月11日 / 養蜂場日記
 ピーヒョロロ~ 養蜂場の上空をトンビが舞っています。澄み切った青空を背景に、高く大きく円を描いて飛んでいます。
ピーヒョロロ~ 養蜂場の上空をトンビが舞っています。澄み切った青空を背景に、高く大きく円を描いて飛んでいます。
紅葉に染まる山々に、長閑な鳴き声が吸い込まれていきます。こちらの心も大空に溶け込んでいくような、開放感を覚えるひと時です。
しかし、この優雅な時間もあまり長続きしないのです。
原因はこの辺りに住み着いているカラス達です。
昔からトンビとカラスは仲が悪いそうなのですが、縄張り意識の強いカラスにとっては、トンビはどうやらその縄張りを荒らす侵入者に写るらしいのです。
一回り体の大きいトンビに対して、複数で攻撃するカラス達。
上から下からの連続攻撃にたまらず逃げ出すトンビ、というのがいつものパターンのようです。
ギャーギャーというなさけない悲鳴をあげて逃げ出すトンビもでる始末。
猛禽という呼び名のわりには、ちょっと情けないトンビ君です。
 毎年、9月末にレンゲの種を播きます。
毎年、9月末にレンゲの種を播きます。