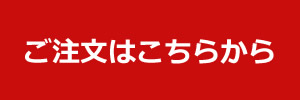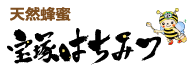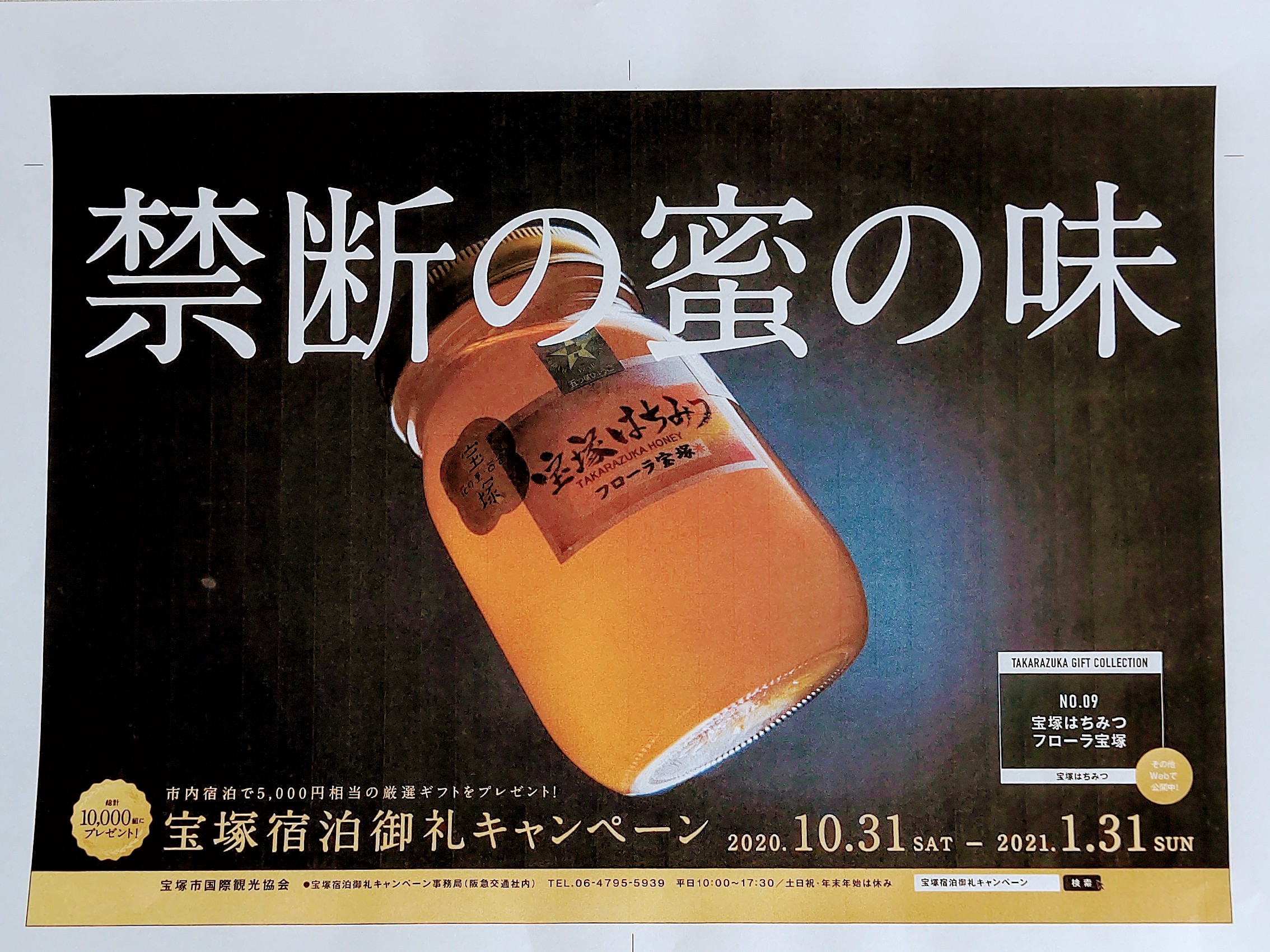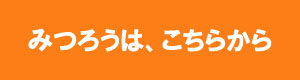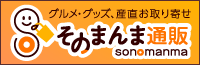養蜂場日記
養蜂家も冬眠?
2010年2月16日 / 養蜂場日記
 冬の間は、繁忙期に比べるとミツバチの世話をする必要はあまりありません。
冬の間は、繁忙期に比べるとミツバチの世話をする必要はあまりありません。
しかし、来季に備えて養蜂場全体の修復・整備・養蜂器具の手入れなど、やらなければならない事は沢山あります。
また、インターネットでの調べもの、瞑想、読書、テレビ、買い物 etc・・・
冬にしかできない事を、ここぞとばかりにできる毎日です。
冬眠中でも、養蜂家は実はゴソゴソと動き回っているのです。
哲平もパソコンでの調べものに付き合って、チェックしてくれているところです。
一ヶ月のご無沙汰でした
2010年2月15日 / 養蜂場日記
 ミツバチも養蜂家も動き出す春です。
ミツバチも養蜂家も動き出す春です。
越冬中のミツバチに余分な刺激は禁物です。
冬の間は養蜂場に行く回数が極端に少なくなります。
外では雪やみぞれが降る寒い日でも、立春の頃になると巣箱の中では女王蜂の産卵が始まり、花の季節への期待が高まっていきます。
巣箱の外でも春の息吹はいたる処に・・・
養蜂場の横の空き地でフキノトウを見つけました。陽だまりの中で、新しい季節への”一番乗り“を宣言しているように見えます。
近くにはオオイヌノフグリの可憐な花の姿も見えます。
旧暦では昨日が元日、養蜂家も春本番への準備に入っていきます。
春を待つ養蜂家
2010年1月15日 / 養蜂場日記
 ミツバチが越冬している今の時期は、養蜂家もゆったりと骨休めのできる時です。
ミツバチが越冬している今の時期は、養蜂家もゆったりと骨休めのできる時です。
小春日和のある日、家の近所を愛犬と散歩していると、どこかから甘い香りが漂ってきました。
香りの主は蝋梅(ろうばい)。
江戸時代から植木栽培で有名なこの地域には、今もたくさんの植木屋があります。
芳香は梅の木を栽培している畑から流れてきていました。
昨年も1月の蝋梅に始まり、2月の紅梅、白梅まで楽しませてくれた場所。
養蜂に明け暮れた一年でしたが、あっという間の12ヶ月でした。
立春の頃から、女王蜂の産卵が本格化してきます。
2月、梅の花が咲き出す頃、養蜂家も活動を再開します。
謹賀新年
2010年1月1日 / 養蜂場日記
 皆様、新年明けましておめでとうございます。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年が皆様にとりまして、幸多き年になりますように。
今年も、より一層美味しい本物の蜂蜜をお届け致します。どうぞ楽しみにお待ち下さいませ。
(写真は、蜂蜜大好きな我が家の小トラです、今年もよろしく!)
ありがとうございました。
2009年12月31日 / 養蜂場日記
今年も出現!
2009年12月19日 / 養蜂場日記
 師走になると田んぼの一角に現われる小屋。
師走になると田んぼの一角に現われる小屋。
早春の食材“うど”を栽培するためのものです。
昔に比べて栽培農家も減り、冬の風物詩としては貴重な存在になってきています。
木枯らしを遮り、日光を遮断する麦わら小屋の中、ウドはどんどん成長していきます。
ウグイスが鳴き始める頃、彼らの出番はやってきます。
食卓に春の香りを届け、本格的な春の到来を告げるのです。
イノシシ君は完全主義者?
2009年12月17日 / 養蜂場日記
 見事に耕された田んぼ?
見事に耕された田んぼ?
その横の土手で、腕組みして考え込んでいた持ち主のNさんがいました。
Nさんによれば、全てはイノシシ君の”夜間作業”の結果なのだそうです。
この田んぼでは、春から夏にかけて野菜類を栽培していました。
その間は電気柵で厳重に囲われており、彼等も踏み込めなかったのです。
収穫が終わり電気柵が外された途端に、地中に残る根菜類や栄養たっぷりの土で育ったミミズ、それを餌として集まるモグラを狙って、イノシシ一家が押し寄せたのでしょう。
それにしても、この完璧な耕しぶりには”お見事!”と脱帽するほかありません。
山里の秋
2009年12月8日 / 養蜂場日記
 山も林も紅葉一色。
山も林も紅葉一色。
養蜂場も紅葉の海に浮かんで見えます。
春夏秋冬、それぞれの顔を見せてくれる自然。
冬枯れの山の斜面のあちこちで、春の到来を告げるコブシの花、ウグイスが鳴き交わす林をピンクに彩る山桜、五月の太陽を浴びて元気よく咲き誇るレンゲ、初夏の生き生きとした新緑の海、真夏の蝉時雨。
目にするもの、聞こえてくるもの全てに、生命の躍動を感じます。四季を体感しながら仕事ができる幸せに感謝!
食後のお仕事
2009年12月2日 / 養蜂場日記
 食後の習慣、歯磨きです。
食後の習慣、歯磨きです。
哲平はご飯のあと、まずハチミツを舐め、次に目薬をさし、歯磨きをして最後にヨーグルトを食べて食後のお仕事?を終わります。
と言っても自分ではやりません、するのは私の役目です。
この歯磨き剤は市販の無糖ヨーグルトです。
ヨーグルトで歯を磨くと虫歯になりにくいということが一時話題になり、それ以来実行しています。
効果はあるみたいですが、ただ、磨きながら盛んにペロペロ舐めるので、ちょっと磨きにくいのが難点です。
ご飯は玄米とおから。市販のフードはおやつに少し与えるだけです。
この食事をもう何年も続けていますが、極めて健康で、元気いっぱいに走り回っています。
ちなみに、目薬も市販のものではなく手作りです、と言っても超簡単!ある液体サプリ(のような物)を精製水で薄めただけのもので、私達も使っています。
続・冬の訪問者
2009年11月30日 / 養蜂場日記
 チュルチュルチュル チュルチュルチュル チューチューチュー♪ 養蜂場が一挙に賑やかになりました、山茶花の花が細かく揺れています。
チュルチュルチュル チュルチュルチュル チューチューチュー♪ 養蜂場が一挙に賑やかになりました、山茶花の花が細かく揺れています。
10羽ほどのメジロの群れがやってきたのです。
冬になると市街地でも目にする、あの鮮やかな緑色の小鳥です。
今日は山茶花についた虫を探しているようです。
こちらの枝からあちらの枝へと敏捷に動き回り、なかなかじっくりと観賞させてくれません。
現在は捕獲や飼育が厳しく禁止されていますが、私の子供の頃は全てが自由でした。
メジロが来る季節になると、思い出すのは故郷のSちゃんのこと。
4歳年上のSちゃんは、メジロ、ヒバリ、ホオジロ等、野鳥の捕獲や飼育についてはまさに名人。いろいろなことを教えてくれました。
雄雌の違いとその見分け方、鳥かごの作り方、罠の作り方、罠の仕掛け方、巣の見つけ方、雛鳥の飼育方法、餌付けの方法等。
小学校低学年の私にとっては、彼は英雄そのもの、とても頼もしい存在でした。
鳥だけでなく、魚とりでも、大人顔負けの技術を伝授してくれる“師匠”でした。
私は生き物が大好きです、博物誌を読み出すと食事も忘れるほど熱中してしまいます。Sちゃんはこの“素晴らしい世界”への門を開いてくれた人です。
養蜂を楽しみながら、さらに周囲の豊かな自然を目いっぱい楽しむことができるのも、Sちゃんが教えてくれたものが土台にあるからだと思います。
ありがとうSちゃん!