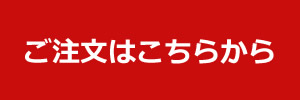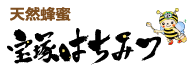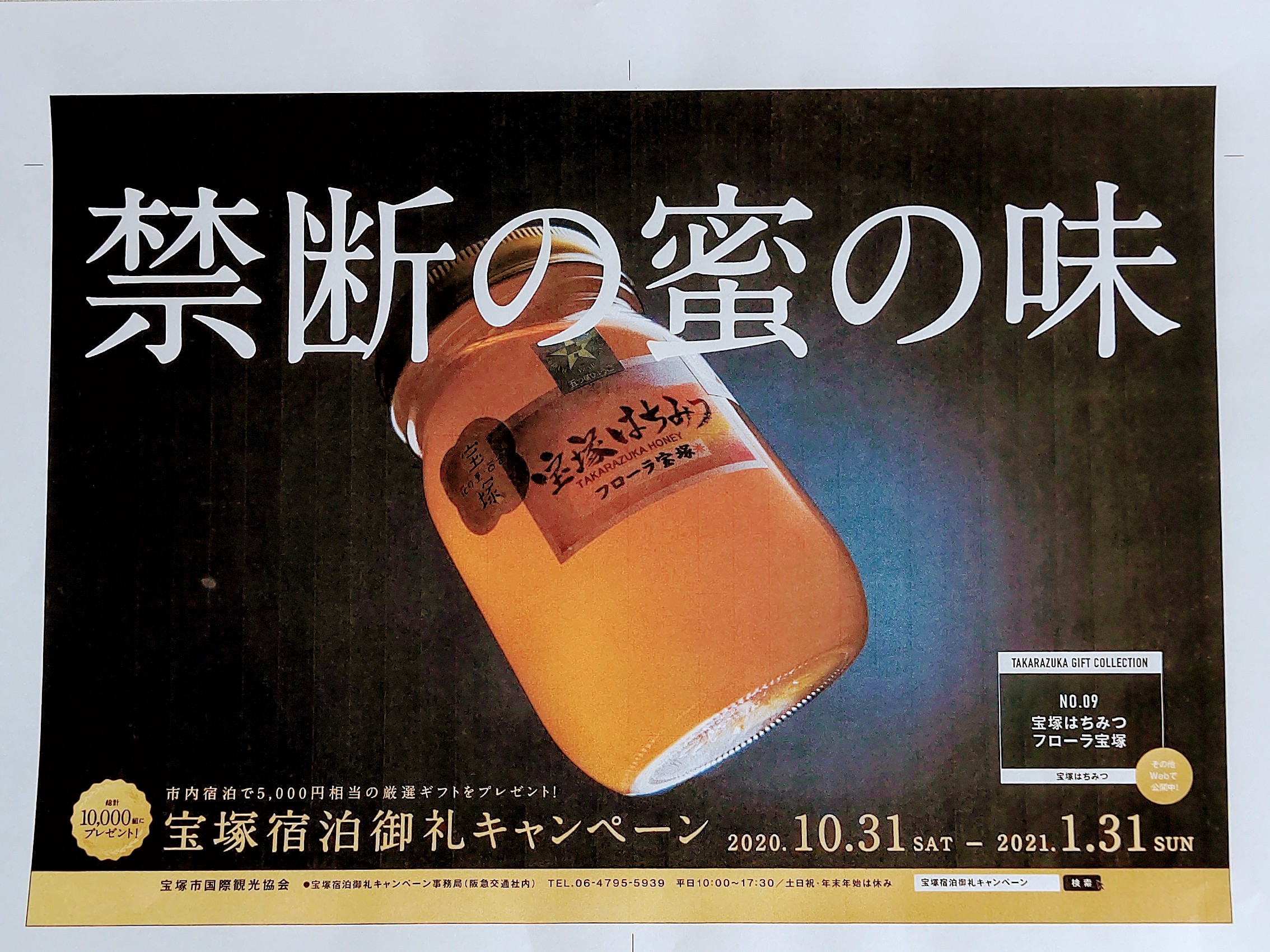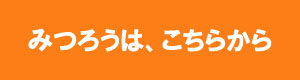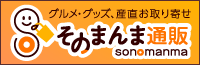養蜂場日記
事件発生!
2013年5月1日 / 養蜂場日記
 巣門の前で働き蜂が円陣を組んでいます。
巣門の前で働き蜂が円陣を組んでいます。
真ん中に何かがいます~~それは女王蜂でした。
息絶えた女王を真ん中にして取り囲み、複数の働き蜂が動かずにただじっと見つめています、まるで女王の死を悼むかのように・・・
養蜂場ではいつも何かが起こっています。
女王の失踪・突然死も珍しいことではなく、よくあることの一つなのです。
ミツバチの世界を垣間見る時、驚いたり、感動したりすることのなんと多いことか!
“神秘の昆虫”といわれる所以はそんなところにありそうです。
思い出の味
2013年4月30日 / 養蜂場日記
 ナワシログミ。
ナワシログミ。
田植えが近付く頃、赤く熟して食べごろを迎える野生のグミ。
九州で過ごした幼い時代、遊び仲間と家の近くの雑木林で夢中になって食べた、懐かしい思い出を運んでくれる季節の果実です。
甘酸っぱい味とともに、サブちゃん、マサコちゃん、ツヨシちゃんなど、懐かしい仲間の嬉しそうな顔が蘇ってきます。
養蜂場のすぐ近くに、偶然2本のナワシログミの木を見つけたのが数年前。
以来、他の誰も知らない“私だけのグミ”として、この季節になると、仕事の合間に実の熟れ具合を確認するのが日課の一つになっています。
タイミングを外すと、ある日、全ての実が忽然と姿を消してしまうのです。
そうなのです!狙っているのは私だけではないのです。
目撃していないので定かではないのですが、おそらく“ヒヨドリ”か“ムクドリ”君たちでなないかと疑っています。
今日はこれだけ(写真)、とりあえず頂くことにしました。
次から次ぎに熟していきます。毎日楽しみですが、もちろん、鳥くんたちにもちゃんと残すようにしています。ご安心を!
ちょっと来い~ えっ?
2013年4月28日 / 養蜂場日記
 今日も朝から元気な鳴声が聞こえてきます。
今日も朝から元気な鳴声が聞こえてきます。
チョットコイ チョットコイ チョットコイ
大きなよく透る声です。その名は“コジュケイ”。
鳴声から取った“チョットコイ”の方が分かりやすいかも知れません。
原産地は中国南部、日本には1919年に持ち込まれ、東京都と神奈川で狩猟用として放鳥されたものだそうです。
今では本州南部、四国、九州の人々にとってはごく身近な存在として親しまれています。チャボくらいの大きさで、 生息するのは草原、森林、竹林、農耕地など広い範囲にわたり、養蜂場の周囲でもひんぱんに目にします。
5月、6月になると7~8羽の子供をつれたコジュケイ夫婦に遭遇し、思わず見とれてしまうことも。
先日は養蜂場の入り口で餌を探しているコジュケイがいました。
鳴声を聞くと不思議と元気が出てくる、山里を代表する鳥です。
分蜂
2013年4月22日 / 養蜂場日記
 巣箱の中に蜂が溢れるような過密状態が長引くと、巣分かれ、すなわち“分蜂”という行動が起きます。
巣箱の中に蜂が溢れるような過密状態が長引くと、巣分かれ、すなわち“分蜂”という行動が起きます。
女王蜂を中心に、全体の3分の一ほどの働き蜂が、新天地を求めて巣から出ていくのです。
この時、すでに巣の中には新しい女王の幼虫が育っている“王台”が数個準備されています。
ほとんどが、晴天で風もなく暖かい日中(午前10時ごろ~午後3時ごろ)に起こります。
巣門から万を越えるミツバチが湧き出して、空中で渦を巻いて飛び交う様子は壮観そのもの。
大半が5月から6月に集中しますが、今年は4月17日に予想外の分蜂が発生しました。
灰神楽ならぬ“蜂神楽状態“。飛び回る蜂の数もさることながら羽音もすさまじく、初めて経験する人は肝をつぶすかも知れません。
しかし、養蜂家にとってはよくあることの一つ、ミツバチが近くの木の枝などに団塊を作って静まるのを待ち、群れを収容、そして一件落着となります。
誕生ラッシュ!
2013年4月21日 / 養蜂場日記
 3週間(21日)で成蜂として誕生する働き蜂。
3週間(21日)で成蜂として誕生する働き蜂。
3月半ばから女王蜂の産卵が盛んになりますが、その数は一日に1000~2000個になります(勿論、1匹の女王蜂の産卵数です)
そして今現在、それらの卵から孵ったミツバチたちが、成蜂となって続々と生まれ出てきています。
1日に1000匹から2000匹が、新しいメンバーとして群れに加わることなるわけです。
“三日見ぬ間の蜂の巣”と言われますが、2~3日の間に巣の中の様相ががらりと変わるのがこの季節。ミツバチたちが、ありとあらゆる空間に所狭しと埋まって?います。
巣箱の蓋の内側まで、ミツバチ達でびっしりと埋め尽くされています(写真)。
こうなると、継箱といわれる貯蜜専用の箱を継ぎ足して空間を広げ、さらに多くのミツバチが収容できるようにしなければなりません。
白い桜
2013年4月17日 / 養蜂場日記
 我が家の“養蜂家”兼“季節のお花配達人”が、昨日、白い花の付いた小枝を持ち帰りました。
我が家の“養蜂家”兼“季節のお花配達人”が、昨日、白い花の付いた小枝を持ち帰りました。
今ごろ桜?しかも真っ白!
養蜂場のある里山は、この辺りの住宅地よりも気温が低く、季節が遅れてやってきます。
桜をはじめとして、季節の花の開花も当然遅れています。でも、さすがに今ごろになって満開になるのは八重桜のはず・・・
実はこれは梨の花だそうです。
5枚の白い花びらの中心が淡い緑色で、桜の花にそっくりです。今迄目にしたこともあったかも知れませんが、白い桜が咲いてるな・・・としか思わなかったのかもしれません。
この辺りでも、秋になるとあのサクサクした歯ざわりの青い実が成るのかな・・・?
梨:4月頃、桜から1週間ほど遅れて開花する。白い5弁花。
風があると実が実らないことから「風なし」これがしだいに変化して「なし」になった。
「梨」は漢名。
養蜂家妻
新種のキノコ?
2013年4月16日 / 養蜂場日記
 しゃもじのような新種のキノコ発見!!・・・ではありません。
しゃもじのような新種のキノコ発見!!・・・ではありません。
この季節、勢いの強い群れでは、次ぎから次ぎに新しい蜂が誕生してきます。
女王の産卵も日を追って盛んになり、産卵場所が不足してくると、ちょっとした空間にも産卵のための巣を作ってしまいます。
こうして作られたもの(写真)は、養蜂家の間で“ムダ巣”といわれ、取り除かれる運命にあるものです。
新しい巣枠を入れることで、“ムダ巣”をつくる“ムダな作業”からミツバチたちを解放することができます。
花とおじさん
2013年4月14日 / 養蜂場日記
 毎年この季節になると、家の中のあちこちに鮮やかな色が出現します。
毎年この季節になると、家の中のあちこちに鮮やかな色が出現します。
我が家の養蜂家が養蜂場周辺の山から頂いてきたものです。
お昼を食べる間も無く一日中働いて、クタクタになりながらも、時々両手に抱えきれない程の、花の付いた木の枝を持ち帰るのです。
作業着を着た地味なおじさんが、夕方、華やかなピンクの花束を抱えて嬉しそうに歩いている姿は、何だか珍しい光景ではないでしょうか?(^^ヾ
しかし5月になると、その枝に色んな虫さんまで付いて来くるので、私はお花を活けながら、時々ギャーッ!と叫んでしまうのです・・・
養蜂家妻
春の贈り物
2013年4月13日 / 養蜂場日記
 現在の里山は、ミツバツツジと山桜に彩られています。
現在の里山は、ミツバツツジと山桜に彩られています。
遠目にも鮮やかな赤紫のミツバツツジと薄桃色の山桜が、未だ灰色にくすんだ冬枯れの雑木林のあちこちに、浮かぶように出現しました。
毎年感じる“春極まれり”といった山里の4月です。養蜂家にとって至福の季節到来です!
さらに、今年のミツバチの成育状況は申し分なく、養蜂家の士気は上がりっ放しという状態です。
今日は、ふんだんに自生しているミツバツツジの花を、少し折り取って持って帰ることにしました。
毎年恒例の、家内へのプレゼントです。
 3月に入り、所用のため2度ほど九州(福岡)を訪れました。
3月に入り、所用のため2度ほど九州(福岡)を訪れました。