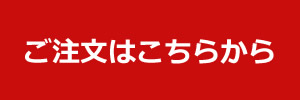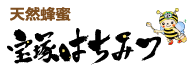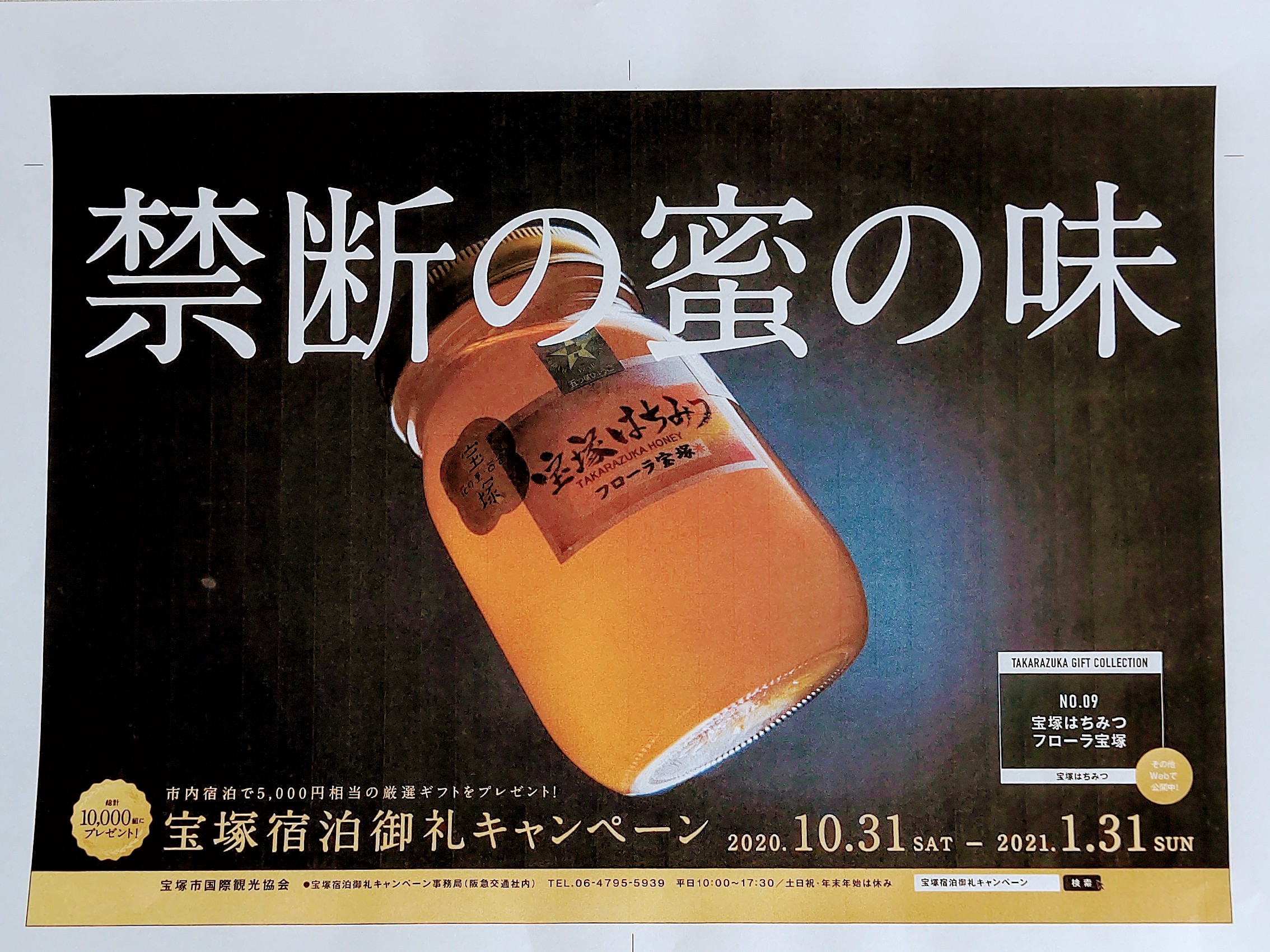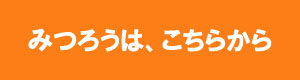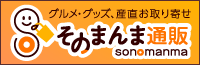養蜂場日記
早朝から張り切っています!
2013年5月29日 / 養蜂場日記
 しばらく養蜂場日記を休みましたが、養蜂家は夜明けからこんなことをしていました。
しばらく養蜂場日記を休みましたが、養蜂家は夜明けからこんなことをしていました。
今は採蜜の季節。一年の集大成の時なのです。
夜明け前に家を出て、夜明けと共に作業を始めます。
夜間、ミツバチたちはその日集めてきた花蜜の水分をとばす作業をします。
早朝には密度の高い、つまり糖度の高い、甘く美味しい蜂蜜が出来上がっていることになります。
採蜜作業が早朝に行なわれるのは、この糖度の高い、美味しい蜂蜜を収穫するためです。
起床午前3時、夕方、一日の作業を終えて家に帰るともうぐったり、とても養蜂場日記まで手が回りません。
しかし、今日から天候は梅雨の前哨状態、養蜂場日記の時間が取れそうです。
花粉の貯蔵庫
2013年5月17日 / 養蜂場日記
 花粉は子育ての必需品。
花粉は子育ての必需品。
高たんぱく質の花粉は、ミツバチの子育てには欠かせません。
彼等は花の季節に沢山の花粉を巣房に貯えます。
花によって花粉の色はそれぞれ違います。
養蜂家はミツバチが運びこむ花粉の色によって、その時何の花が開花しているのかを知るのです。
巣房にはいろんな色の花粉が貯えられています。
これらは全て、働き蜂が団子のように丸めたものを両足に付けて、せっせと運び込んで来たものなのです。
新緑の朝
2013年5月13日 / 養蜂場日記
 朝日に新緑が輝いています。
朝日に新緑が輝いています。
新緑の林からいろいろな野鳥の声が聞こえてきます。
一日の始まりです。
あまりにも清々しい光景に、養蜂家は陶然とした気持ちにひたっています。
こんな素晴らしい自然の中で“神秘の昆虫”といわれるミツバチを相手に一日を過ごすことは、何ものにも勝る喜びです。
養蜂をやっていて良かった~と思うひと時でもあります。
野薔薇の蜂蜜
2013年5月11日 / 養蜂場日記
 荒牧バラ公園に行ってきました。
荒牧バラ公園に行ってきました。
最盛期には1万本の薔薇が咲きますが、まだ6部咲きといったところでした。
“薔薇にミツバチ“の写真を撮りたかったのですが、ミツバチが全く飛んでいません。まだこれからなのでしょうね。
ここに巣箱を置かせて貰ったら、薔薇の蜜が取れるのにな~と思ったことがありました。
でもこういう施設では、薔薇に虫が付かないように消毒するのでしょうから、蜂蜜を取るには適していませんね。
以前うちの蜂蜜の花粉検査をしてもらったところ、百花蜜には野薔薇の花粉が入っていました。 ~里山の野薔薇の花蜜の入った百花蜜、ぜひご賞味下さい~
養蜂家妻
荒牧バラ公園
南欧風の園内に250種1万本のバラが植えられています。開花時期は5~6月と10~11月で、特に5~6月はたくさん咲き乱れてすばらしい光景になります。
世界の薔薇、約250種 1万本の薔薇が咲き誇ります。
↓詳しくはこちらをご覧ください。写真が綺麗です!
http://barakou.com/
天気晴朗なれど霧深し?
2013年5月10日 / 養蜂場日記
 早朝の山間の道、視界10メートル。
早朝の山間の道、視界10メートル。
5月からは、ほぼ毎日、夜明けの道を養蜂場に急ぎます。
山間部は霧が発生しやすく、写真のようなことも頻繁に起こります。
こんな時は、日中気温が上がり、しかも抜けるような青空で風もない、まさに養蜂日和とでも言いたいような一日になるのです。
しかし、快適なのは人間だけでなく、ミツバチにとっても同じこと”巣別れ”つまりは”分蜂”に最適の条件を備えた日でもあります。
養蜂家にとっては、分蜂は群れの採蜜力が半減する大きな損失、どうしても避けたいこと。
そんな危険をはらんだ濃霧発生に、養蜂家の心は波立っています。
実は虫が苦手?!
2013年5月8日 / 養蜂場日記
 緑が輝く季節になりました。
緑が輝く季節になりました。
我が家の養蜂家は、待ちに待った季節の到来!とばかりに、日の出と共に養蜂場に出かけます。
1日中休みなしでミツバチの世話をして、クタクタになって帰宅します。
そしてまた翌日、元気いっぱい喜々として、朝早くからミツバチ達の元へ~
どこからそんなエネルギーが湧いてくるのか、不思議に思います。
毎日毎日、ミツバチ達が出す無限の”8”のエネルギーを浴びているからでしょうか?
どんなに忙しくても大変でも、楽しくて堪らないそうです!
そんなに好きな仕事に打ち込めて充実した時を過ごせるなんて、なんと幸せなのだろう!と羨ましく思ってしまいます。
私は逆に、子供の頃から虫が大の苦手!たまに夫が服のどこかにミツバチを付けて帰ることがあり、部屋の中を1匹ブンブン飛び回るだけで大騒ぎです!
オオスズメバチと違い、こちらが何もしなければ滅多に刺すこともない大人しいミツバチさん。とても可愛いんですけどね(^^ヾ
養蜂家妻
出戻り分蜂
2013年5月6日 / 養蜂場日記
 ひときわ大きな羽音が響き始めました。
ひときわ大きな羽音が響き始めました。
やってくれました!またまた分蜂です。
この忙しい時に、少しは遠慮してくれよ~と言いたくなります。 巣門からは湧き出すように蜂が飛び出しています。
すぐに巣門にトラップを仕掛けます。働き蜂は通り抜けられますが、身体の大きな女王蜂とオス蜂は、入ると出られなくなる仕掛けになっています。
分蜂は女王蜂がいなくては成立しません。いったん巣箱を飛び出した万を越える働き蜂たちは、女王蜂がいないことに気付くと、いっせいに巣箱に戻り始めます。
写真は戻ってきた蜂たちがトラップの周囲を取り囲み、大きな団塊になった状態です。
我も桜!
2013年5月5日 / 養蜂場日記
 その名は”ウワミズザクラ”
その名は”ウワミズザクラ”
白いブラシのような花をつける一風変わった桜の仲間です。
ソメイヨシノが終わり、その後に盛期を迎えるのが山桜。
そして山桜の開花が一段落する頃、登場してくるのがこの“ワレモサクラ”君。
6年前、養蜂場に植えた2本の苗木が成長し、今年、初めてその1本が花をつけてくれました。
そろそろ咲くのではと思っていた矢先でしたが、何気なく向けた目にその白い花が飛び込んできた時は、やはり嬉しく、思わず声を上げていました。
未だ花の数は少なく、よく見ないと見落とすぐらいですが、いずれ樹木全体が白く見えるほど見事な姿を披露してくれるでしょう。
名歌手“イソヒヨドリ”
2013年5月3日 / 養蜂場日記
 早朝から作業を始めている養蜂家の耳に、ひときわ澄み切った鳴声が聞こえてきました。
早朝から作業を始めている養蜂家の耳に、ひときわ澄み切った鳴声が聞こえてきました。
一日の幕開けにふさわしい、朗々とした歌いっぷりに思わず聞きほれてしまいます。
最初の頃は“黒ツグミ”だと思っていたのですが、たまたま、家の近くの梢で鳴いているのを目撃して、この名歌手がイソヒヨドリであると確信しました。
本来は磯や海辺の断崖などに生息している鳥です。海から遠く離れた山間部にある養蜂場で鳴声を聞けるはずがないと思っていましたが、“内陸部に住み着くこともある”という説明、“宝塚の市街地で目撃”という事実から、イソヒヨドリであると確信するにいたりました。
名前からヒヨドリの仲間と思ってしまいますが、正しくは“ツグミ科”の鳥だそうです。
写真がうまく撮れなかったので、ウィキペディアからお借りしました。
 巣門の前で働き蜂が円陣を組んでいます。
巣門の前で働き蜂が円陣を組んでいます。